
冬至はエネルギーが変化する分岐点として、日本や中国、またケルトでも、大切な日とされてきましたが、
ハロウィンの大元は、ケルト伝承「サマイン」であり、
秋分と冬至の中間点、立冬のことであり、本格的な「寒さ」に向うことを示します。
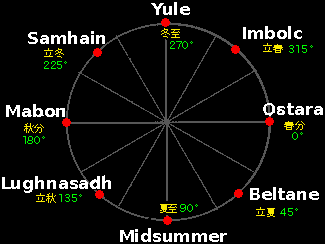
つまり、どんどん日が短くなることに備えての「お祭り」がハロウィンですが、
冬至とは「新しい光」が示される日であり、クリスマスで「新しい光」を祝うのです。
さて、昨年の冬至は、銀河の中心のセントラルサンと太陽、地球がほぼ一直線に並び、
そのせいかどうか、眠りがヤケに浅かったのですが、
今年は目覚まし時計を電磁波フリーにチェンジしたおかげかどうかわかりませんが、
ぐっすり眠れ、6時に目が覚めたら素敵な朝日が拝めました。
 東京都八王子市6時半頃、
東京都八王子市6時半頃、
 月もくっきり見える晴天の中、
月もくっきり見える晴天の中、
 東の空がだんだんオレンジに染まり、
東の空がだんだんオレンジに染まり、
 見事なグラデーションの中、新しい昇ります・・
見事なグラデーションの中、新しい昇ります・・

中国では冬至の日に「餃子」を食べて祝うそうですが、
日本では「かぼちゃ」がポピュラーで、ケルト民族と同じく、かぼちゃのオレンジに太陽を感じたのかもしれませんが、
「かぼちゃ」には西洋かぼちゃと日本かぼちゃがあり、

かぼちゃを冬至に食べる風習は,江戸時代中期に根づいたと言われてますが、現在広く流通しているのは「くりかぼちゃ=西洋かぼちゃ」で、
日本かぼちゃより西洋モノが甘味が強くカロチンも豊富です。
西洋かぼちゃは南米ペルーあたりが原産ですが、南半球に位置する南米では冬至は夏至となり、今、南米は真夏です。
山梨県南部町で自然農をはじめた純日本人だけどもペルー生まれの友人、
 ペルーラム君は、あえて苦手な食べ物を挙げると「かぼちゃ」だそうですが、
ペルーラム君は、あえて苦手な食べ物を挙げると「かぼちゃ」だそうですが、
かぼちゃは、すこぶる栄養素の高い健康食材です。
かぼちゃは、β-カロチン(ビタミンA)が豊富なほか、ビタミンB1、B2、C、カルシウム、鉄などをバランスよく含んだ栄養面ですぐれた野菜です。
この数多い栄養成分の中でも、含有量の多さで目をひくのがβ-カロチンです。
近年、このビタミンAが風邪、C型肝炎などの感染症やガンといった免疫力低下によって発症する病気の抑制に効果的であることで注目されています。
β-カロチンには、粘膜などの細胞を強化して、免疫力を高める働きがあります。
免疫力が高まると、外から体内に侵入してくる有害な細菌やウイルスを撃退するだけではなく、抗がん作用も高まります。さらにβ-カロチンには、体を酸化から守る坑酸化作用もあります。
体内の細胞の酸化は、ガンや老化など様々な病気の原因となっています。かぼちゃには、β-カロチンに加えてポリフェノールやビタミンC、Eなどの抗酸化成分が豊富に含まれており、抗酸化力が極めて高い野菜です。
冬至に食べるとよいといわれるのは、その時期、かぼちゃを常食していると、風邪の予防になると考えられるからです。
ビタミンAとCが粘膜の抵抗力を高め、細菌感染を予防する効果を発揮します。体力がなく、貧血ぎみの方が常食すれば、鉄分、カルシウム、ビタミンCなどの効果で、症状が改善されるでしょう。
胃や腸の潰瘍に、かぼちゃのポタージュがよく飲まれます。これはカロチンとビタミンCに、細胞粘膜を正常に保つ効果があるとされるからです。
かぼちゃのビタミン類、ポリフェノール、ミネラル、食物繊維等は、皮やワタに多く含まれています。
ちなみにビタミンAとビタミンEは脂溶性なので、油と一緒に調理すると体内での吸収率が良くなります。
かぼちゃだけ食べていればOKそうな栄養源ですが、
実際のところ。「不食」で有名なジャスムヒーンさんが、完全不食に至る過程で、

5年間は1日300カロリー以下で過ごしたのですが、その期間のメイン食は「かぼちゃ」でした!
興味深いことに、この期間中、私が摂取するように導かれた物質は生姜とかぼちゃのみで、これらは両方とも私たちの脳波のパターンをシータ場に接続させる化学物質の生産を促すものと知られています。
いわゆるサイキック現象はシータ波の脳波パターンが関係しており、
生まれつきのサイキックであるペルーラム君が「かぼちゃ」苦手なのは、不食には興味ないからでしょうか?
いずれにせよ、かぼちゃには胃腸の調子を整え、身体を温めるはたらきがあり、風邪予防になり、この季節にはうってつけの「神々の食べ物」であり、
カロリー高めなかぼちゃですが、ゆくゆくは不食も可能にするかもしれませんので、
冬至の日は「新しい光」と共に、「かぼちゃ」を楽しみましょう!
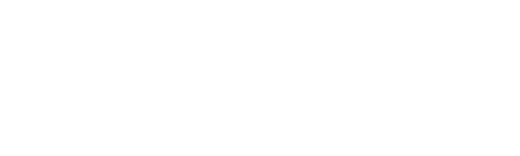




COMMENT ON FACEBOOK