台湾が中国に対してミサイル発射をした・・という英国ニュースは、
英国の元記事がフェイクだったいうご指摘があり、
この件に関しては、「くまさん」の早とちりだったかもしれませんが、いずれにせよ、今、米中情勢が要注意なのは事実です。
そして近々、「再生計画」をしなくてはならないほど、地球が追い詰められてる一番の要因は、
「中共の横暴にある」と、地球管理の宇宙人と交流ある坂本廣志氏は述べてましたが、
マドモアゼル愛さんの最新動画で、「法輪功学習者への臓器狩り」を知り、
「中共の横暴」の一番の被害者は中国国民であることを改めて認識しました。
中国の伝統的な健康法である気功に基づいて、李洪志が1992年に公にした気功修練法、及びその団体である。
1999年より江沢民政権下の中華人民共和国は、法輪功を邪教と定め活動禁止とし、弾圧を始めた。以後、法輪功の実践者たちは中国共産党政権の司法、警察、政治的な迫害を受けており、裁判令状のない逮捕、拘束、収容所における死に至るほどの虐待や拷問が続いている。
そういえば坂本氏情報でも、「マック商品に混じっとる子供肉は中国のものです」ということでしたが、
ナント、「人肉食」は古代から脈々と行われてきたとのことです。
**********
Q:▪️①インドネシア〜アフリカ、中国の②直接人肉食はいつ頃の話? ミヨイ国は日本・沖縄・台湾や①とも陸続きやったの? そうならミヨイ黄人も②しとったん?
A:▪️ポン太様、①インドネシア〜アフリカ、中国の②直接人肉食はいつ頃の話かは、始まって以来現在もそうです。 ミヨイ国は日本・沖縄・台湾や①とも陸続きでした。そうならミヨイ黄人の一部インドネシアも②していました。
**********
「生贄」とか、古代の方々にとってフツーだったわけで、しかし21世紀、水瓶座の時代となった今でも「アル」とは驚きですが、映画などのエンタメの世界には、その片鱗が垣間見れます。
例えば、大昔(20代後半)に見た「コックと泥棒、その妻と愛人」という映画は、ラストの復讐シーンがあまりにも衝撃的でよく覚えてますが、
1989年製作のイギリス・フランス合作映画である。ピーター・グリーナウェイ監督・脚本。
ストーリー
大泥棒のアルバートは、今夜も自らが経営するフレンチ・レストラン”ル・オランデ”(Le Hollandais)を訪れていた。グルメを気取っているものの味が分からず、この上なく身勝手で誰彼構わず粗暴な振る舞いをするため、フランス人シェフのリチャードはアルバートを嫌っていたものの、恐れから追い出すことはなかった。
アルバートの妻ジョジーナは夫から虐待されており、彼女も夫を恐れていた。やがてジョジーナはレストランの常連である本屋で学者のマイケルに惹かれるようになり、二人はリチャードの計らいもあって、レストランの厨房で逢引するようになる。しかし、やがて二人の関係はアルバートにばれてしまい、悲劇的な結果を迎える。
悲嘆にくれるジョジーナは、リチャードに助力を請い、アルバートにあるおぞましい方法で復讐を遂げるのだった。
愛人を泥棒に殺された妻の「復讐」は、愛人の死体をリチャード(コック)に調理してもらい、泥棒に食べさせ、「人喰い!」の烙印を押すことで、
この映画は、人間味のない経済政策の行く末を示唆してると見る向きがあります。

ピーター・グリーナウェイ監督の『コックと泥棒、その妻と愛人』の舞台は、華美な装飾に彩られた高級フランス料理店。主な登場人物は、タイトルが物語るように、料理店のシェフ、毎晩特等席を占領して店を牛耳る泥棒、この泥棒に虐げられる妻と彼女の愛人になる本好きの物静かな紳士の4人である。
グリーナウェイの作品には毎回、映像に様々な仕掛けがほどこされているが、この映画では色へのこだわりが際立っている。舞台となる料理店は、店内が赤、厨房が緑、化粧室が白に明確に色分けされ、しかも登場人物が色の違う空間に移動するたびに、衣服が微妙に変わっていたりする。
しかし、そんな映像の仕掛けよりもまず強烈な印象を残すのが、店を牛耳る泥棒の徹底した悪党ぶりだ。善悪の基準など軽々と超越し、世界の秩序や構造をシニカルに眺めているようなグリーナウェイが、ここでは悪の存在というものに並々ならぬこだわりをみせる。そんな悪党に虐げられる妻は愛人を作り、それを知った泥棒は愛人に報復し、最後に妻は夫に復讐する。これまでになくドラマチックな展開である。
グリーナウェイは背景が80年代であること以外、舞台を特定していないが、これがサッチャリズムを意識した物語であることは容易に察することができる。サッチャーはロンドンを世界経済の中心地にするために、再開発を押し進めた。この映画の舞台となる高級料理店は、そのジェントリフィケーションの産物である。そして、サッチャリズムを支えるのは、極悪非道な泥棒というわけだ。
この映画の凄いところは、欲しいものを手に入れるためには手段を選ばないこの泥棒の欲望を、すべて食べるという根源的な行為を通して描いてしまうところにある。映画の冒頭では、ひとりの男がこの泥棒の手で汚泥を口に押し込まれ、見せしめにされる。妻と愛人を庇った厨房の少年は、泥棒につかまり、ボタンを口に押し込まれて、殺されてしまう。そして、読書家の愛人は、本のページを口に押し込まれ、息の根を止められる。
泥棒のこの非道な所業は、サッチャリズムの社会では、神も知識もまったく意味がないことを表している。少年は厨房でいつも、罪を悔い、神に許しを求める歌を歌い、愛人は料理店でいつも本を読んでいた。少年は信仰を、愛人は知識を象徴している。ただ貪欲なまでに食べるしかない社会のなかでは、信仰も知識も意味を失い、排除される。そして、サッチャリズムが行き着く先には、おぞましいカニバリズムが待っているのだ。
サッチャリズムは、高福祉の社会保障政策「ゆりかごから墓場まで」を推し進めましたが、
それが失敗であったことは、「わたしは、ダニエル・ブレイク」などで描写される英国の現状で見てとれます。
大英帝国は中国と「アヘン戦争」になった歴史があり、
今回の「台湾が中国に対してミサイル発射をした」ニュースの出どころが英国というのも気になるところで、
武漢発「コロナ」問題もあり、三共ダムと同じく、中共は「決壊」寸前という感じですが、
これ以上「追い詰めると危険」な面もあり(核保有国ですから)、
ひじょーに、さじ加減が難しい・・局面に、世界は「今」あるようですが、
いずれにせよ「裁く」のではなく、慈悲の気持ちで、今なお行われている残虐行為の事実を世界中の人々が「認識する」ことで、

内部からの「浄化」が起きることを切に願います。
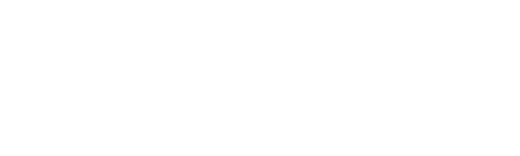

COMMENT ON FACEBOOK